-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
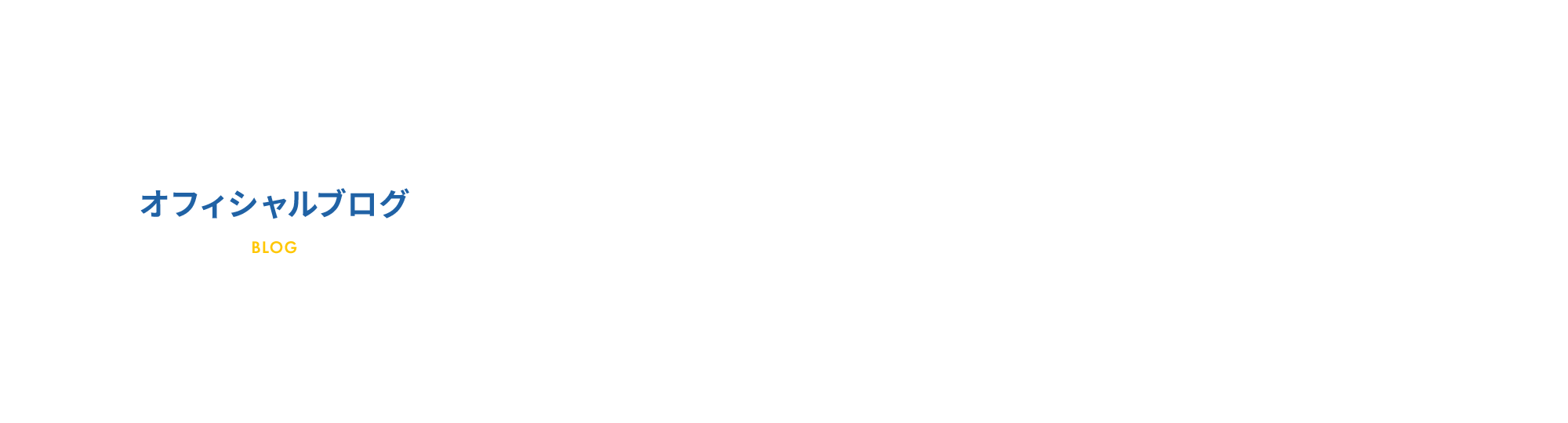
皆さんこんにちは!
CLEAN TECH JAPAN、更新担当の中西です。
~ターンオーバー清掃~
民泊清掃業という言葉は、ここ10年ほどで一気に市民権を得た印象がありますよね😊
でも本質は、ただのハウスクリーニングでも、ホテルメイクでもありません。
民泊には民泊特有の事情があります👇
だから民泊清掃は「掃除」+「準備」+「品質管理」+「運用」のセット。
この“セット化された清掃”が、民泊の拡大とともに独立したサービス産業として育っていきました📈✨
Airbnbなどの登場(2008年)から、日本で民泊が拡大し、2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行で「清掃がルールとして要求される」流れまでを、歴史として追っていきます🧹📚
1)起点は2008年:プラットフォームが「個人宅を宿泊施設」に変えた🛏️📱
民泊の世界的な転換点として語られるのが、Airbnbの登場です。Airbnbは2008年に米サンフランシスコで創業したと整理されています。
ここで起きた革命は、建物を作ったわけでも、ホテルを増やしたわけでもなく、“空いている部屋”を市場に変えたこと。
すると何が起きるか?
これまで宿泊業の清掃は「ホテル・旅館の裏方の標準業務」でしたが、民泊では違います。
ここから「民泊清掃」という新しい仕事が芽を出します🌱✨
2)日本での土壌:訪日需要の伸びと、宿泊ニーズの多様化✈️🗾
2010年代、日本では訪日観光が伸び、宿泊の需要も多様化していきます。
その流れの中で、民泊は「ホテル不足を補う」「家に泊まる体験」「長期滞在」「家族・グループ向け」として広がりました。
宿泊が分散し、物件が増えるほど重要になるのが――
**“物件を毎回同じ品質に戻す仕事”**です🧹✨
ここで民泊清掃が、単なる掃除から「運用インフラ」になっていきます。
3)黎明期の課題:清掃が追いつかないと、民泊は回らない😣🧺
民泊が増え始めたころ、現場ではよくこんな問題が起きました。
つまり、清掃の失敗は衛生だけでなく、運営そのものを止めます。
この頃から「ターンオーバー(入れ替え)清掃」の型が作られていきます🔁
✅ターンオーバー清掃が“作業”から“仕組み”になったもの
ここで民泊清掃は、業務として“業界化”していく準備が整います。
4)決定打は2018年:住宅宿泊事業法(民泊新法)施行で「清掃・衛生」が義務として明確に📜🧼
日本では民泊が急増する一方、無許可営業や衛生・騒音・ゴミなどの課題が社会問題化し、ルール整備が進みます。国土交通省(観光庁)による制度説明では、住宅宿泊事業法は2017年6月に成立し、2018年6月15日に施行されたとされています。
また、同制度では年間営業日数の上限(180日)も明示されています。
この“制度化”が、民泊清掃業にとって大きな意味を持ちました。
なぜなら、清掃は「やった方がいい」から「やらなければならない」へ変わったからです。
観光庁の事業者向け説明では、届出住宅の設備・備品を清潔に保ち、定期的な清掃・換気を行うこと、シーツ等は宿泊者が入れ替わるごとに交換することなど、衛生確保の考え方が示されています。
つまり、民泊運営における清掃は“品質オプション”ではなく、遵守すべき衛生管理として位置づけられたわけです🛡️✨
5)「清掃の外注」が当たり前になり、専門業者が増えていく🏢🤝
民泊新法では、運営形態により管理業務の委託が関わる場面も整理され、清掃を含む実務を専門業者に行わせるケースについても、観光庁の案内で考え方が説明されています(ただし責任の所在はケースにより整理されます)。
ここから起きた現実的な変化はこれ👇
こうして民泊清掃業は、2018年前後を境に「副業的な手伝い」から「専門サービス」として厚みを増していきます。
民泊清掃業は、プラットフォームと法整備によって“宿泊インフラ”になった🧹✨
CLEAN TECH JAPANでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()

民泊を運営していて、こんな不安はありませんか?
• 「最近レビューが★4.6→4.3に落ちた」
• 「特に悪いサービスをした覚えがない」
• 「掃除は毎回しているのに、なぜか低評価がつく」
実は、福岡市の民泊で低評価レビューがつく原因の約8割は清掃に関係しています。
立地や価格ではなく、「清掃のわずかな差」が評価を左右しているのが現実です。
この記事では、
福岡市で実際によくある民泊清掃の失敗例と、
レビューを落とさないための具体的な対策を解説します。
⸻
なぜ福岡の民泊は清掃で評価が下がりやすいのか?
福岡市は
• 観光客
• 出張ビジネス客
• インバウンド
が混在しており、宿泊者の清潔基準が非常に高いエリアです。
特に多いのが👇
• ホテル慣れした宿泊者
• Airbnbを何十回も利用しているユーザー
こうした人たちは
「汚れているかどうか」ではなく
「完璧かどうか」で評価します。
⸻
レビューが下がる民泊清掃の失敗例5選(福岡市で多発)
① 髪の毛が1本残っている
最も多い低評価理由です。
• 洗面所
• ベッド周り
• 浴室の排水口
👉 実際のレビュー例
「全体的に綺麗だが、洗面所に髪の毛が落ちていた」
★5 → ★3になる原因は、たったこれだけ。
⸻
② 水回りの“白残り・黒ずみ”
• 洗面台の水垢
• シャワーのカビ
• トイレの縁汚れ
オーナー側は見慣れてしまっていても、
宿泊者は一瞬で判断します。
⸻
③ 床・ソファの見落とし
福岡の民泊はワンルーム・1LDKが多く、
• 床のベタつき
• ソファ下のゴミ
• ラグの汚れ
が目立ちやすい構造です。
⸻
④ ニオイ問題(これが一番致命的)
• 前の宿泊者の体臭
• 食べ物のニオイ
• 排水口臭
👉 ニオイ系レビューは
★1〜★2がつきやすく、致命傷になります。
⸻
⑤ アメニティ・備品の不備
• トイレットペーパー残量不足
• タオルの生乾き臭
• ゴミ袋がない
「清掃はされているが、気配りが足りない」
=低評価につながります。
⸻
なぜこれらのミスが起きるのか?
原因はほぼ共通しています。
• 1人作業で確認不足
• 清掃時間が足りない
• チェックリストがない
• 毎回同じ目線で掃除している
特に繁忙期(週末・連休・イベント時)は
「間に合えばOK」になりがちです。
⸻
プロの民泊清掃がやっている3つの対策
① 2人1組で役割分担
• A:床・リネン・全体
• B:水回り・備品・最終確認
👉 見落としが激減します。
⸻
② 時間管理された清掃工程
「この部屋は何分で、どこまで仕上げるか」が決まっているため、
品質にムラが出ません。
⸻
③ 宿泊者目線の最終チェック
• 玄関を開けた瞬間の印象
• ニオイ
• 水回りの第一印象
オーナー目線ではなく、初宿泊者目線で確認します。
⸻
福岡市の民泊は「ホテル基準」でないと評価は守れない
福岡は競合民泊が非常に多く、
宿泊者は比較に慣れています。
• 「前の宿はもっと綺麗だった」
• 「この価格なら当然」
という目線で見られるため、
ホテル清掃レベルが事実上の基準になっています。
⸻
レビューを落とさないために、今できるチェック
✔ 髪の毛ゼロを確認しているか
✔ 水回りを最後にチェックしているか
✔ ニオイ対策をしているか
✔ 清掃後に“客の目線”で入室しているか
1つでも不安があれば、
レビューが落ちる前に対策することが重要です。
⸻
福岡市で民泊清掃を外注するという選択肢
民泊運営は
「集客・価格調整・レビュー管理」が本業です。
清掃で評価を落とすのは、
最も避けるべき損失と言えます。
福岡市で
• レビューを安定させたい
• 清掃品質を均一にしたい
• 繁忙期でも任せたい
という方は、
ホテル品質の民泊清掃を検討してみてください。
福岡市で民泊清掃のご依頼の個人様、法人様は一度弊社へご相談ください。
https://www.instagram.com/clean_tech01?igsh=Nzhjam9jY3Q1ZDFj&utm_source=qr

民泊の稼働率を上げたいなら「清掃の質」が最重要な理由
☆レビュー評価を伸ばし、安定収益につなげる民泊清掃の考え方
民泊運営において、
「なかなか予約が増えない」
「レビュー評価が伸び悩んでいる」
そんな悩みを抱えているオーナー様は少なくありません。
実はその原因、清掃の質にあるケースが非常に多いことをご存じでしょうか。
民泊における清掃は、単なる掃除作業ではありません。
ゲスト満足度・レビュー・稼働率・収益すべてに直結する、運営の中核です。
本記事では、民泊清掃がなぜここまで重要なのか、そしてプロの清掃を導入することで何が変わるのかを解説します。
⸻
民泊で「清掃」がレビュー評価を左右する理由
民泊ゲストが最も厳しくチェックしているポイントの一つが、
**「清潔感」**です。
・水回りに髪の毛が残っている
・床のホコリや砂
・ニオイ
・アメニティの不足や補充漏れ
これらは小さなことのようで、レビューでは大きなマイナス評価につながります。
逆に言えば、
清掃が行き届いているだけで高評価レビューを獲得しやすくなる
ということです。
レビュー評価が上がる
↓
予約率が上がる
↓
検索順位が上がる
↓
稼働率・収益が安定する
この流れを作れるかどうかは、清掃の質にかかっています。
⸻
民泊清掃と一般清掃の決定的な違い
「民泊の掃除なら、自分やスタッフで十分では?」
そう考える方も多いですが、民泊清掃には特有の難しさがあります。
① 限られた時間内での高品質清掃
チェックアウトから次のチェックインまで、時間は非常に短い。
スピードと正確さの両立が求められます。
② ゲスト目線の仕上がり
住居用清掃では問題にならない部分でも、
民泊ではクレームにつながることがあります。
③ 清掃漏れ=即クレーム
民泊では「次回で直す」は通用しません。
一回の清掃が勝負です。
このレベルを安定して維持するには、
専門の清掃体制とチェックフローが不可欠です。
⸻
プロの民泊清掃を導入する3つのメリット
1. レビュー評価が安定する
清掃品質が一定に保たれることで、
低評価レビューのリスクが大幅に減少します。
2. 運営の手間が減る
清掃手配・確認・連絡対応から解放され、
オーナー様は集客や物件拡大に集中できます。
3. 突発対応にも強い
連泊・延泊・急な予約変更にも、
柔軟に対応できる体制を構築できます。
⸻
CLEAN TECH JAPANの民泊清掃が選ばれる理由
CLEAN TECH JAPAN(クリーンテックジャパン)では、
民泊・ホテル清掃で培ったノウハウを活かし、
民泊運営に最適化した清掃サービスを提供しています。
✔ 民泊特化の清掃チェックリスト
水回り・寝具・床・アメニティまで、
ゲスト目線で細かくチェック。
✔ スピードと品質の両立
限られた時間内でも、妥協のない仕上がりを徹底。
✔ 安心の報告体制
清掃完了報告により、オーナー様も状況を把握できます。
✔ 福岡エリア対応
福岡市を中心に、民泊清掃の実績を積み重ねています。
⸻
民泊清掃でお悩みのオーナー様へ
・清掃が追いつかない
・レビュー評価を改善したい
・清掃品質にバラつきがある
・運営の負担を減らしたい
そのお悩み、清掃をプロに任せることで解決できます。
民泊は「清掃が整った瞬間から、安定運営が始まる」と言っても過言ではありません。
⸻
民泊清掃のご相談・お見積りはお気軽に
CLEAN TECH JAPANでは、
物件規模や運営スタイルに合わせた最適な清掃プランをご提案します。
👉 民泊清掃のご相談・お見積りはこちらから
清掃から、民泊の成功を一緒につくりましょう。
皆さんこんにちは!
CLEAN TECH JAPAN、更新担当の中西です。
“信頼されるプロ”
ホテル清掃というと、「誰でもできそう」と思われることもあります。
でも実際に現場に入ると分かります。ホテル清掃は、想像以上に“プロの世界”です
時間管理、品質管理、衛生管理、チーム連携…すべてが求められます。
ここでは、ホテル清掃業が“価値ある仕事”として評価される理由と、キャリアとしての魅力を深掘りします✨
目次
ホテル清掃は、限られた時間で最高の品質を作る仕事です。
チェックアウトからチェックインまでの間に、複数の部屋を仕上げなければならない現場もあります
ただ急げばいいわけではなく、品質が落ちればクレームにつながる。
この「早く、正確に、美しく」を両立するのがホテル清掃の難しさであり、面白さです✨
慣れてくると、自分の動きがどんどん洗練されていきます。
無駄のない手順、道具配置、動線、作業順…。
成長が目に見える仕事なので、スキルが積み上がる実感があります
ホテルは不特定多数の人が利用します。
だからこそ、衛生の基準がとても重要です✅
特に水回りやリネンは、お客様の安心に直結します
例えば
消毒・除菌の手順
手袋の使い分け
クロスの使い分け(拭く場所で分ける)
️ ゴミ処理の衛生管理
こうした基本を徹底することで、“見えない安心”が生まれます✨
ホテル清掃は、清潔さを作るだけでなく、安心を提供する仕事でもあるのです
ホテル清掃はチームワークが非常に大切です。
客室担当、共用部担当、リネン管理、チェッカー(最終確認)など役割が分かれている現場も多く、連携がうまくいくほど全体の品質が上がります✨
「この部屋、備品が足りない」
「この汚れ、特殊だから共有しよう」
「チェックインまでにこのフロアを仕上げよう」
こうした声かけが、現場の力になります
人間関係が良い現場ほど働きやすく、仕事の質も上がる。
ホテル清掃は“チームで作るおもてなし”でもあります
ホテル清掃では、気づく力がとても重要です。
ホコリ、髪の毛、拭きムラ、匂い、備品の配置の乱れ…小さな違和感に気づける人は、どんどん信頼されます
そしてこの観察力は、仕事以外にも活きます。
家庭の掃除が早くなる
段取りが上手くなる️
気配りが自然にできるようになる
日常にもプラスになるスキルです
ホテル清掃は経験を積むと、キャリアの道も広がります。
✅ チェッカー(品質管理)
✅ 現場リーダー
✅ 新人教育担当
✅ 清掃プランの改善提案
✅ 衛生管理の責任者
「ただの作業者」ではなく、“品質を作る人”へ成長できます✨
ホテル業界は今、清掃品質の重要性がさらに高まっています。
だからこそ、清掃のプロはこれからもっと求められる存在です
CLEAN TECH JAPANでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
CLEAN TECH JAPAN、更新担当の中西です。
“おもてなしの最前線”
ホテルに泊まったとき、部屋に入った瞬間の第一印象ってとても大きいですよね
ベッドがピシッと整っている️✨
床や水回りが清潔で気持ちいい
タオルがふわっと香っている
ゴミひとつ落ちていない――。
この「気持ちよさ」は、偶然ではありません。そこにはホテル清掃のプロの技術と気配りがあります
ホテル清掃業は、ただ掃除をする仕事ではありません。
お客様が心から休める空間をつくり、ホテルの評価を支え、旅や仕事の疲れを癒す“おもてなしの最前線”です
目次
今は口コミの時代。
「部屋がきれいだった」「水回りが清潔だった」「気持ちよく泊まれた」
この一言が予約を増やし、ホテルの価値を上げます✨
逆に、どれだけ立地が良くても、どれだけ接客が丁寧でも、
「部屋が汚れていた」「髪の毛が落ちていた」
たった一つの不満で評価が下がることもあります
だからこそホテル清掃は、ホテルの品質そのものを守る仕事。
清掃スタッフは“裏方”ではなく、ホテルの信用を作る主役の一人です
ホテル清掃のすごさは、やったことが“目立たない”ことです。
完璧に整った部屋ほど、お客様は「当たり前」に感じます。
でもその当たり前は、プロの手順とチェックの積み重ねでできています✅
例えば
️ ベッドメイク:シワを作らず、角を揃え、見た目を均一に
水回り:水垢・石鹸カス・カビの兆候を見逃さない
鏡・ガラス:拭きムラをゼロに
リネン:匂い、汚れ、毛羽立ちのチェック
アメニティ:配置の“美しさ”と補充の正確さ
床:髪の毛一本でも見つける観察力
こうした細部への集中力が、快適な滞在を作ります✨
つまりホテル清掃業は、細部を整える職人仕事でもあります
ホテル清掃は、1部屋ごとに状態が違います。
長期滞在の部屋、ファミリー利用の部屋、ビジネス利用の部屋…。
その部屋の“使われ方”に合わせて、必要な清掃が変わります✨
でもどんな部屋でも、最終的には「新品みたいな状態」に戻す。
この“リセットして整える”作業は、やり終えたときの達成感が大きいです
終わった後に部屋を見渡して、
「よし、完璧」
と思える瞬間があるのも魅力です️✨
ホテル清掃は動きの多い仕事です。
ベッドメイク、掃除機、拭き上げ、リネン交換、備品補充…全身を使います♀️
適度に汗をかけるので、運動不足解消にもつながるという声もあります
また、ホテルによっては日中帯の勤務が中心で、生活リズムを整えやすいのもメリット✨
家庭との両立、Wワークなど、柔軟な働き方ができる現場も増えています️
ホテル清掃の仕事は、気づきの連続です。
「ここにホコリが溜まりやすい」
「この部屋は乾燥しやすいから加湿器の水を確認しよう」
「お子様連れっぽいから備品の配置も安全に」
こうした気配りが、宿泊体験を静かに底上げします✨
清掃スタッフの仕事は、お客様と直接会話しなくても“おもてなし”ができる仕事。
その優しさが、空間として伝わるのです
CLEAN TECH JAPANでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
CLEAN TECH JAPAN、更新担当の中西です。
「快適な滞在は清掃から生まれる」
目次
ホテルのホスピタリティは
フロントやコンシェルジュだけではありません。
むしろ、
一番お客様と長い時間接しているのは
客室清掃が整えた空間。
ベッドに入る瞬間
洗面台を使った瞬間
バスルームに入った瞬間
カーテンを開けた瞬間
フロアに足を踏み入れた瞬間
そのすべてが
“清掃品質”に左右されます。
ベッドメイク
掃除機
バスルーム清掃
備品補充
排水トラップのニオイ対策
消毒・除菌
床や壁の隅の汚れ
水垢防止コーティング
カーテンのホコリ落とし
エアコンフィルター
これら見えない部分こそ、
プロの清掃品質を決めるポイントです。
ホテル清掃では
1部屋につき30〜50項目以上のチェックがあります。
鏡に水滴がないか
バスルームのゴムパッキンは黒ずんでいないか
ベッドシーツはシワがないか
枕の配置は正しいか
TVリモコンは定位置か
ゴミは残っていないか
床の角にホコリがないか
これはホテルブランドを守るための必須工程。
ホテル清掃の象徴といえば
やはりベッドメイク。
シーツの角を美しく折るプロ技術。
フワッと清潔感あるシルエットを作る。
叩いて空気を入れ、ふんわりさせる。
たった1台のベッドにも
“職人技”が詰まっています。
ホテル清掃では
ウイルス対策の強化により基準が大幅に上昇。
✔ 高頻度接触部(ドアノブ・スイッチ)消毒
✔ 換気の徹底
✔ 空気清浄機の導入
✔ 除菌スプレーの標準化
✔ リネン類の高温殺菌洗浄
清掃スタッフは
“お客様の見えない不安まで取り除く仕事”をしています。
ホテル清掃は、段取り力が全て。
無駄のない動きが求められます。
時間内に多数の部屋を仕上げる。
雑な仕上げはホテル品質ではNG。
小さな汚れも見逃さない。
意外とハードな仕事。
清掃は“お客様のために整える仕事”。
大きなホテルでは
清掃スタッフ
チーフ
ランドリー
バックヤード担当
マネージャー
多くのスタッフがチームで動きます。
連携がうまくいくホテルほど
清掃品質が高くなります。
ホテル清掃は、
お客様の安心・快適・リラックスを支える
“プロのホスピタリティ”。
見える部分の清掃
見えない部分の管理
ベッドメイク
水回りの徹底
チェックの正確さ
衛生基準
チームワーク
これらを完璧に整えて
はじめて“ホテルのおもてなし”が生まれます🏨✨
CLEAN TECH JAPANでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
CLEAN TECH JAPAN、更新担当の中西です。
「ホテル清掃は“おもてなしの基礎”」
目次
ホテルの印象の8割は、
“客室の清潔さ”で決まると言われています。
ホコリがない
シーツがパリッとしている
バスルームがピカピカ
ゴミが残っていない
匂いが清潔
備品が整っている
ベッドが美しい
これらはすべて、清掃スタッフの技術と努力の成果。
チェックアウトから次のチェックインまでの間に
数十室〜数百室を整える必要があります。
そのため清掃は👇
すべてのバランスが求められる、非常に高度な仕事です。
ホテルによって異なりますが、基本的には以下の流れです。
まず換気して空気を入れ替えます。
ゴミ箱・冷蔵庫・ベッド下までチェック。
シーツ・ピロケース・デュベカバーを外す。
ホテル品質の核心。
シワなく、ピシッと美しいベッドを作る技術が求められます。
排水
鏡
洗面台
トイレ
シャワー
水垢・髪の毛・カビ対策が要になります。
歯ブラシ
タオル
シャンプー
スリッパ
ティッシュ
ホテルごとに細かいルールがあります。
隅々までゴミが残らないように。
清掃リーダーやチーフが最終チェック。
ホテル清掃は、
「正しい順番で丁寧に行う」プロの仕事です。
特に難しいのがベッドメイク。
熟練スタッフは
“1分以内で美しいベッド”を作る技術を持っています。
バスルームは汚れが目立ちやすく、
ニオイの原因にもなります。
ホテル清掃では👇が必須。
水垢除去
鏡のウロコ取り
排水口チェック
カビ対策
トイレ清掃の徹底
最後の水切りで仕上げ
「まるで新品」のように仕上げます。
髪の毛・ホコリは絶対に残さない。
空気清浄・消臭・換気を徹底。
ホテルの品格が出るポイント。
ミリ単位のズレもホテルではNG。
見落としやすい部分まで確認。
数百枚のシーツ・タオルを専用のランドリーへ。
どの部屋が清掃済みかを素早く共有。
アメニティ・清掃道具を整理整頓。
時間内に仕上げるため、連携は必須。
清掃の質が良いと👇
クチコミ評価が上がる
リピーターが増える
客単価が上がる
ホテルのブランド価値が向上
まさにホテルの根幹を支える仕事です。
ホテル清掃は、
お客様の“安心と快適”をつくり出す、
ホテル運営の最も重要な仕事。
ベッドメイク
バスルーム清掃
アメニティ管理
衛生チェック
時間管理
チームワーク
これらを丁寧に積み重ねて
ホテルの“おもてなし品質”が生まれます🏨✨
CLEAN TECH JAPANでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
CLEAN TECH JAPAN、更新担当の中西です。
~ホテルの裏方が主役!?~
ホテル清掃の仕事は、「裏方」と思われがちですが、
実は“ホテルの品質”を左右する大切な存在なんです
どんなに豪華なホテルでも、部屋が汚れていたらお客様の印象は最悪に
だからこそ、清掃スタッフの仕事はホテルの“顔”ともいえます✨
ベッドメイキングの美しさや、バスルームの輝き、タオルの折り方一つにも“おもてなしの心”が表れるんです️
限られた時間で何部屋も仕上げるためには、段取りとチームワークが命
1つの動きもムダにせず、息を合わせて作業を進める様子はまるで職人の現場
一見シンプルな仕事に見えても、実は奥深い“プロの技術”が詰まっています✨
清掃の仕事は体を動かすため、健康的でリズムのある働き方ができます♀️
また、完成した部屋を見て「今日も頑張った!」と達成感を味わえるのも魅力
静かな空間でコツコツ集中できるので、黙々と作業が好きな人にもピッタリです
清掃スタッフは、ホテルで働くすべての人の中でも特に「お客様に寄り添う存在」。
気配り・丁寧さ・スピード――そのすべてが一つになって“心地よい滞在”を生み出します
誰かの旅の思い出の一部になる✨
そんな素敵な仕事、それがホテル清掃業なんです
CLEAN TECH JAPANでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
CLEAN TECH JAPAN、更新担当の中西です。
~お客様の「快適な一日」をつくる!~
ホテルに泊まったとき、「部屋がピカピカで気持ちいい!」と思った経験はありませんか?😊
その快適さをつくっているのが、実は“ホテル清掃スタッフ”なんです💪✨
ホテル清掃は、ただ部屋をキレイにするだけではありません。
お客様が気持ちよく過ごせるように、ベッドのシワ一つ、鏡の指紋一つにも気を配ります👀
「次に入るお客様の笑顔を想像して」
そんな気持ちで一つひとつの部屋を整えるのです💖
まさに“見えないおもてなし”のプロフェッショナル🌸
ベッドメイク、バスルームの清掃、アメニティの補充など、限られた時間で完璧に仕上げるスピードと正確さが求められます⏱️
「どうしたらもっと効率よく、でも丁寧にできるか」
日々の中で工夫を重ね、チーム全体で成長していく――そこにやりがいがあります💪🌈
チェックインしたお客様が「わぁ、きれい!」と声を上げる瞬間✨
そのたびに「今日も頑張ってよかったな」と心が温かくなります😊
清掃の仕事は、“快適な時間”と“癒し”を提供する最高のサービスなんです🌺
CLEAN TECH JAPANでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
CLEAN TECH JAPAN、更新担当の中西です。
~やりがい~
目次
フロントの笑顔や客室のデザインより前に、ゲストが無意識に評価するのは「清潔さ」。
見えないホコリ一つ、指紋一つが満足度を左右し、再訪・口コミ・客単価に直結します。
ホテル清掃は“裏方”ではなく、ブランド体験の起点です。
衛生の確かさ:高接触部位(リモコン・スイッチ・ドアノブ等)の確実な消毒
一貫した品質:日や担当者が変わっても同じ仕上がり
静けさと配慮:滞在中清掃の声・音・動線の気遣い
可視化:清掃完了カード、アプリ通知、封印シールなど“やった”が分かる安心
ターン時間の最適化:チェックアウト〜インの“山”を崩さず間に合わせる
人手不足対策:省人化と新人戦力化(教育の短サイクル化)
コスト×品質の両立:リネン・消耗品・洗剤の最適使用
エコ運用:連泊時の選択清掃、リネン交換頻度の設計、食品・資材ロスの抑制
安全と人間工学:腰・肩に優しいツール、PPE、無理のないノルマ
手順の明確化:誰でも迷わないスタンダード(SOP)
評価の見える化:成果が数字で返ってくるやりがい
ビフォー/アフターが“秒で分かる”達成感
乱れた客室が整っていく充足感。写真で並べると小さな工夫も価値に変わる。
ゲストの安心をつくる誇り
「清潔でぐっすり眠れた」の一言が、何よりのエネルギー。
職人技×チームプレー
ベッドメイクの手際、目地の汚れを一発で落とすコツ、動線設計——技術が成果に直結。
改善が数字に跳ね返る手応え
1室あたり3分の短縮、苦情率0.2pt改善、レビュー4.6→4.7……小さな積み上げがホテルの収益を押し上げる。
多様な働き方に優しい
時短・シフト柔軟・語学不問でも活躍でき、キャリア(検査員・教育担当・管理者)も描ける。
高接触チェックリストを導入 → クレーム半減
ゲストの安心が口コミに反映され、予約サイト評価が上昇。
“見える清掃”の採用(完了カード+封印) → 連泊率UP
目に見える配慮がリピーターを生む。
ワゴン動線の再設計 → 1フロア10分短縮
同じ人数で清掃可能室数が増え、オーバーブッキングリスクも低減。
高接触20点ルール
リモコン/スイッチ/ハンドル/蛇口…“20点だけは必ず触る”を徹底。写真付きSOPで新人も迷わない。
三色タオル方式
赤=水回り、青=客室、緑=鏡・ガラス。交差汚染を防ぎ、検査も一目で判断。
5枚撮り報告
入室・ベッド・バス・デスク・退室の5カットをアプリ記録。教育とトレーサビリティに直結。
連泊“選択清掃”の標準化
タオルだけ、ゴミだけ、フル清掃を選べる。資源・時間を賢く配分。
ワゴン“定盤”化
上段:補充、中央:清掃、下段:リネン。全館同一配置で応援・ヘルプ時も迷わない。
客室清掃時間(分/室):山谷別の中央値で管理。外れ値は原因分析。
再手直し率(%):1%未満を目指し、発生箇所をヒートマップ化。
レビュー清潔度(5段階):週次で推移確認、コメントキーワードを教育に反映。
連泊エコ選択率(%):環境貢献と工数削減の両輪KPI。
労災・ヒヤリハット件数:ゼロ目標。要因別に対策(滑り・持ち上げ・化学剤)。
※大切なのは“他社比較”より“自館のベースラインを上げ続けること”。
DX:PMS連携で空室ステータス即時更新、モバイル配車で待機ゼロへ。
ロボット:廊下・ロビーは自律清掃、人は“細部の仕上げ”と検査に集中。
サステナブル:低香料洗剤、節水ノズル、リネンの再生素材、廃棄の分別徹底。
ウェルビーイング:腰部サポート器具、軽量ワゴン、休憩導線の再設計で離職を防ぐ。
ホテル清掃業は、
衛生・一貫品質・省人化・環境配慮という強いニーズに支えられ、
見える達成感・ゲストの安心・数字で伸びる手応えという大きなやりがいを生む仕事。
“見えないところほど丁寧に”。
その積み重ねがブランドを育て、再訪と口コミを呼び、現場の誇りを高めます🧹🛏️🌿
CLEAN TECH JAPANでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()